【幼児教育の豆知識】子どもに学習習慣をつけさせるには? 親として注意すべきことについて徹底解説!
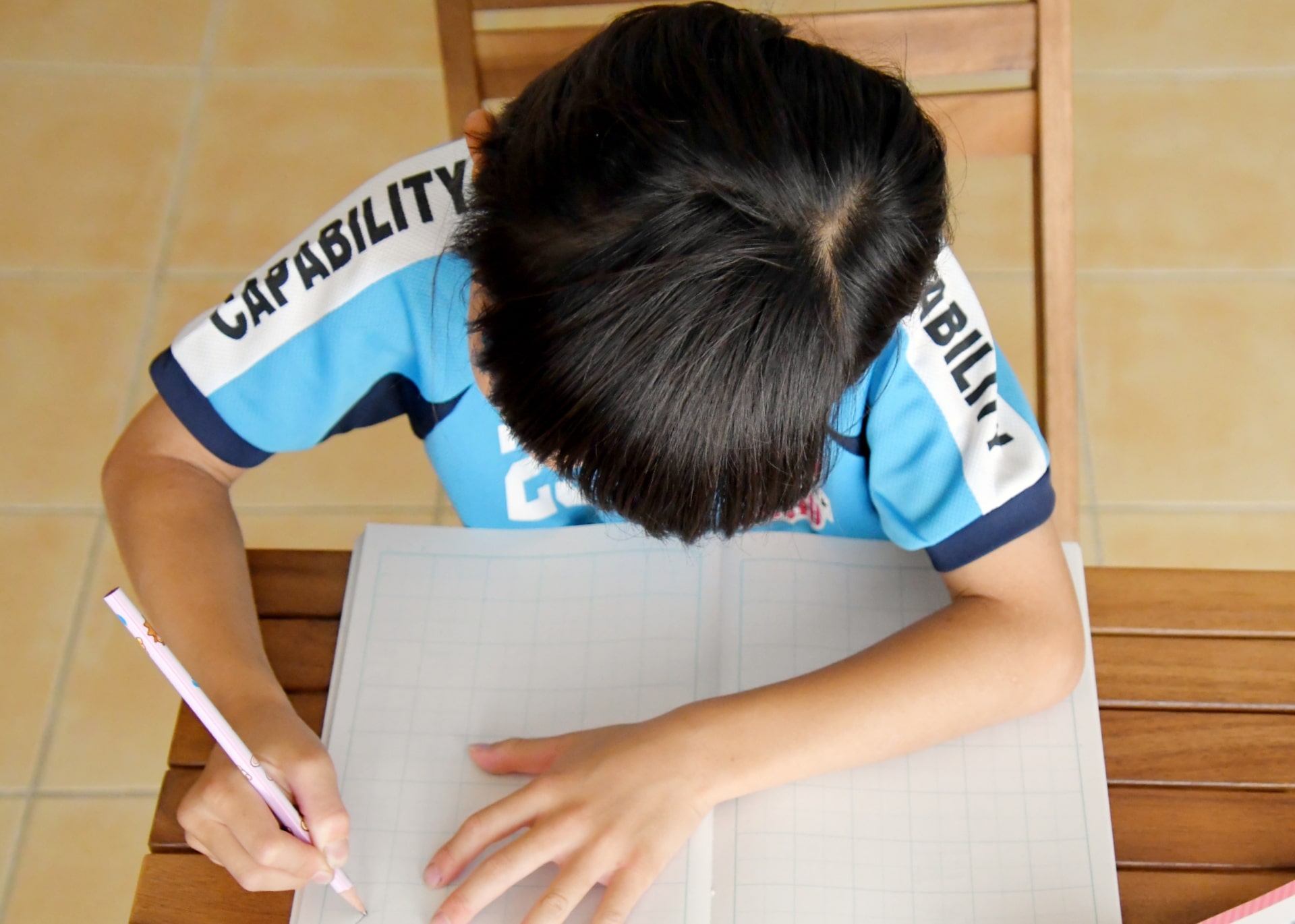
小学校入学が近づいてくると、「そろそろ子どもに学習習慣をつけさせたい」と思う親も多いでしょう。小中高大と進学していくうえで、日ごろの学習習慣が大きく影響してきます。でも、放っておいたら自然と勉強してくれる、という子はまれではないでしょうか。特に幼児期から低学年は親の指導と見守りが必要です。
そこで今回は、子どもに学習習慣をつけさせるために必要なこと、避けるべきことを中心に紹介。すでに子どもが小学生という人も、ぜひ参考にしてくださいね。
小さなうちから学習習慣をつけさせるメリット
子どもの年齢が上がれば上がるほど、学習習慣をつけるのはハードルが高くなります。できるだけ幼いうちに学習を日常の一部としてしまうのがベスト。そうすれば子どもの心理的負担が少なくなるだけではなく、将来につながるメリットもあるのです。
学ぶ楽しさが分かる
「勉強はしんどい」「つらいもの」と感じてしまう子どもも残念ながら少なくないよう。しかし、本来学びとは人の知識欲を満たしてくれる「楽しい」行為であるはずです。幼いころから少しずつ学びを続けて、わからないことがクリアになるという成功体験を積み重ねていくことは、「学びの楽しさ」へとつながっていきます。
「学ぶことが楽しい」と感じられれば、誰に言われなくてもどんどんと知識を探求し、自ら学び成長し続けるようになります。
自分で考え、行動する力が付く
学習習慣をつけさせる上で大切なのは、親がなんでも決めてしまうのではなく子どもを主体に一緒に決めていくこと。幼いころから自分で目標を立て、いつ、どのくらい、何を勉強するのかを決めて進めていくことは、「何事も自分で考えて行動していく」という人間力を養います。自分の人生を主体的に生きるこの力は、まさにVUCA(先の見えない時代)に求められているものでもあるのです。
学習習慣は大人になってからも大切
学習習慣は受験、進学のためのものと考えがちですが、その後も長く役立つものです。就職試験はもちろん、社会人になった後も学びは重要。変化のスピードが速い現代社会では、「リスキリング=知識・スキルを学び直し新たな仕事に対応する」がひとつのキーワードです。常に新たな知識を学び、身につけていく人だけが、変化に対応できるのです。幼いころから自発的な学習習慣がついていれば、社会人になってからも無理なく学ぶ姿勢を持ち続けられるでしょう。
子どもに学習習慣をつけさせるための5つポイント
幼いころからつけておきたい学習習慣。でも、やみくもに勉強をさせればいいというわけではありません。親が指導するうえでどんなことに気を付ければいいのか、5つにしぼって解説していきます。
勉強に取り組みやすい環境の準備
特に年齢が低い子どもは、すぐに集中力が切れやすく気がそれてしまうことも。まずは勉強を始めやすく、集中しやすい環境を作ってあげることから始めましょう。
小学校入学を機に専用の子ども部屋を設ける家庭もありますが、勉強部屋として使うのは高学年以降というパターンが多いようです。低学年の場合は一人で勉強するのが難しいことも多いもの。昨今メジャーになっている「リビング学習」なら、親が家事をしながらほどよい距離感で見守ることができます。ただ、テレビをつけたり兄弟が遊んだりしていると気が散るもとに。テレビや音楽機器は消して、子どもの視野にゲームやおもちゃが入らないように片付けておきましょう。
無理のない姿勢でノートを書けるよう、机といすが子どもの体に合っているかもチェックを。足が床に着かない場合は台を用意してあげると落ち着いて座っていられます。また、リビングは勉強するには明るさが足りない場合も。暗い中で勉強するとノートに顔を近づけすぎて姿勢や目が悪くなることもあります。デスクライトを用意してあげるといいでしょう。
レベルや性質に合わせた教材の選択
子どもが使用する教材選びも重要。通信教育や書店で販売されるドリルなど実にさまざまな教材がありますが、難しすぎるものも簡単すぎるものも子どものモチベーションを下げてしまいます。親は子どもがどの程度理解しているのかを把握し、その実力に見合ったレベルの教材を選びましょう。
また、同じパターンの問題を黙々と解くのが得意な子もいれば、違う科目を次々にやりたい子もいます。使用している教材や進め方が子どもの性質に合っているかのチェックも忘れずに。
適正な目標の設定
「なぜ勉強しなくてはいけないの?」というのは、子どもにしたら当然抱く疑問です。勉強の目的は受験や進学のためだけではなく、人生の豊かさにつながることではありますが、特に年齢が低いとピンとこないかもしれません。その場合は、「次のテストで95点以上を取る」など近くてわかりやすい目標を立ててみても。親ではなく子ども自身が目標として設定することができれば、やる気も出やすいでしょう。
勉強する時間や内容を決める
服を着替える、ご飯を食べるといった行動は毎日の中で特にがんばらずにできること。それはルーティンになっているからです。勉強を「がんばって取り組むもの」ではなく、「毎日当然やるもの」にするためには、ルーティン化してしまえばいいのです。
そのためには、いつ勉強するか、どのくらい勉強するかなどを決めておくことが大切。たとえば、「学校から帰宅して、おやつを食べた後に1時間」としたら、基本的にそれを守るようにします。
朝が得意な子どもであれば、少し早めに起きて「朝ごはんの後に30分」でもいいでしょう。中学受験などの入試は朝から行われるもの。早朝の勉強習慣をつけておくと役に立ちます。
勉強する内容も、月曜日は国語、火曜日は算数、など決めておくと取り組むのもスムーズです。
いずれにしても、親が勝手に決めるのではなく、できそうかどうかを子どもと相談しつつ、一緒に決めていくと続きやすくなります。
親子で一緒に学習
子どもだけに「勉強しなさい」といって親がスマホを見ているようでは、子どもは「なぜ自分だけ…」という不公平感を抱くかもしれません。「大人になったらどうせ勉強しなくなるのに」と、今学ぶことに疑問を持つ原因にも。
子どもが勉強に意欲を持てるように、親も一緒に机に向かってみましょう。もちろん、家事などで忙しいこともありますし、長時間でなくてもいいのです。家計簿をつけたり、読書をしたりもいいでしょう。「親も学ぶのが普通」という状態が、子どもを机に向かわせるきっかけとなります。
親がしてはいけないこと
子どもの学習習慣をつけるうえで親の指導は大切ですが、親の関わり方によっては逆に勉強する気を削いでしまうという場合もあります。そんな「親がさけるべき言動」の具体例をまとめました。いずれもありがちなことなので、チェックしておきましょう。
勉強しなさい、と口うるさく言いすぎる
あまりにも親が口うるさく言うと、逆効果になってしまうこともあります。例えば5時から勉強、ということにしていたとしましょう。親は、5時が近づいてくると「もうすぐゲームの時間は終わりよ!」と予告をすることも多いでしょう。5時になれば「早く宿題をしなさい!」、少し過ぎたら「勉強はどうなっているの?」。立て続けに「勉強」「勉強」といわれてしまうと、子どもはプレッシャーを感じ、勉強することに対して反発を覚えてしまうのです。
勉強する時間を一緒に決めたなら、定刻に一度コールする程度にとどめて、子どもが自発的に行動するのを見守るようにしてみましょう。
テストの点数で子どもを判断する
テストの結果が良いと、親としては「よくやったね!」と単純にほめたくなりますね。ただ、点数だけにフォーカスしてほめていると、がんばったのに点数が悪かったときにはどうでしょう。「勉強したけれど、点数が取れなかったから自分はダメだ」と、子どものモチベーションや自己肯定感が下がってしまいかねません。
点数=結果だけで子どもの良し悪しを判断せず、その過程、つまりどれだけ準備したか、勉強してきたかを評価してあげることが大切です。
兄弟や他の子と比較する
子どもに何とか勉強してほしいからといって、「〇〇くんはいつも2時間勉強しているそうよ」とか、「お兄ちゃんはいつも100点だったのに」などと、他の子を持ち出してくるのは避けたほうがいいでしょう。
「親にできないと思われている」と感じると子どもの自信は低下し、勉強への意欲をそぐことにつながりかねません。
比較するのであれば、「以前よりすぐに勉強に取り掛かれるようになったね」「以前に比べて集中力がアップしたね」など、子ども自身の過去からステップアップしたことに注目してあげましょう。
教材を与えすぎる、無理に長時間やらせる
効果があるといわれる教材は親としては気になるもの。しかし、あれもこれも購入して、長時間の勉強時間を設定する、ということになると子どももついていけなくなります。
特に低学年の間は、まず勉強する習慣をつけることが第一。子どもに合わせて30分程度の無理のない学習時間を設定し、宿題とプラスαの学習を行っていきましょう。教材も、その時間内でできる程度の量とし、子どもに合っているようであればコロコロと変えずにしばらく続けて様子を見ます。

それでも子どもが勉強したくないというときは
いろいろと試したものの、子どもの学習習慣がつかない、ということもありえます。親は叱りたくなるのをぐっとこらえて、子どもの気持ちに寄り添う対応をすることが必要です。
どうしてやりたくないのかを直接聞いてみる
まずは、どうして勉強をしたくないのかをずばり聞いてみましょう。ただし、怒りながらではなく、子どもが話しやすいように落ち着いて聞くこと。
子どもの理由は、例えば「取り掛かるのがめんどう」「ゲームがもっとやりたい」かもしれませんし、「算数のかけ算はよくわからない」といった勉強内容についてかもしれません。その理由に合わせて、改善策を考えてみましょう。
遊びからの切り替えが難しいようであれば、「宿題をしてから遊ぶようにしようか」「終わってから1時間ゲームの時間を作ろうか」など提案を。
勉強内容が難しいなら、つまずいているところを一緒に見なおし、理解を助けてあげるとスムーズに学習に取り組めるかもしれません。
スモールステップでもできたことをほめ、勉強の成功体験を積み重ねられるようにする
いくら叱っても、勉強嫌いの子が翌日から180度変わる、というのは難しいものです。親の理想や定めた目標に到達しないからといって、「できていない」ことばかりを指摘すると子どものやる気はおこりません。
「できていない」ことではなく、どんな小さなことでもいいので「できたこと」を見逃さず、ほめてあげるようにしましょう。「毎日30分勉強」の予定が10分しかできなくても、「10分は机に向かえたね。がんばったね」というようにほめます。「一度言われただけでゲームをやめられた」「字が前よりきれいになった」などどんなことでもいいのです。親に「できた」と認められることで、子どもの中に勉強の成功体験ができ、「また次もがんばろう」という土台となっていきます。
なぜ勉強してほしいのか、親の気持ちを改めて伝える
なかなか学習習慣が付かない子どもは、自分の中で「毎日勉強しよう」という意欲が持てない状態。そんなときにただ「勉強しなさい」と言い続けても効果はありません。親はいったん立ち止まり、「なぜ子どもに勉強してほしいのか」を今一度考えてみましょう。
「学習習慣をつけることで、自己管理ができるようになってほしい」「知識を増やすことで知的刺激がいっぱいの楽しい人生を送ってほしい」など、出てきた答えは率直に子どもに伝えてみます。
「親がどういう理由で勉強を勧めるのか」が分かるだけでも、子どもの学習への向き合い方が少し変化するはずです。
まとめ
「もっとやってみたい」と思えるように、学ぶ楽しさを感じられる工夫を
楽しいことは自ら積極的にやるのが子どもです。勉強も楽しいと感じられれば、自然と家庭での学習にも身が入るでしょう。
机上で学んだことを日常で体感するのは、勉強の楽しさを感じられるひとつ。買い物で値段を計算してもらう、調味料など身近なものを使って簡単な実験をする、近くの工場見学へ行くなど、知識と日常がつながる体験をさせてあげるのもおすすめです。
子どものペースややり方を考慮しながら、学習習慣を作っていこう
最適な学習の仕方は人によって異なります。「宿題は帰宅後すぐ」と決めたけれどどうしてもやる気が出ず、朝早く起きてやった方が集中できた、ということもあるかもしれません。同じ小学一年生でも30分集中できる子もいれば、20分で疲れてしまう場合も。親は「こうしなくてはならない」という思い込みにとらわれず、子どものペースややり方に合わせて学習習慣を一緒に作っていくようにしましょう。

株式会社ヘーグル 理事長
30年以上にわたって、幼児期からの理想的な能力開発と学習環境を追求、独自に開発した「親と子の共育大学のプログラム」など、親子でともに成長できる子育て、教育メソッドは絶大なる人気を誇る。

【執筆者】逸見 浩督(へんみ ひろただ)
株式会社ヘーグル 理事長
30年以上にわたって、幼児期からの理想的な能力開発と学習環境を追求、独自に開発した「親と子の共育大学のプログラム」など、親子でともに成長できる子育て、教育メソッドは絶大なる人気を誇る。








