【幼児教育の豆知識】気を付けたい子どものスマホ依存 予防策から対応策まで徹底解説!
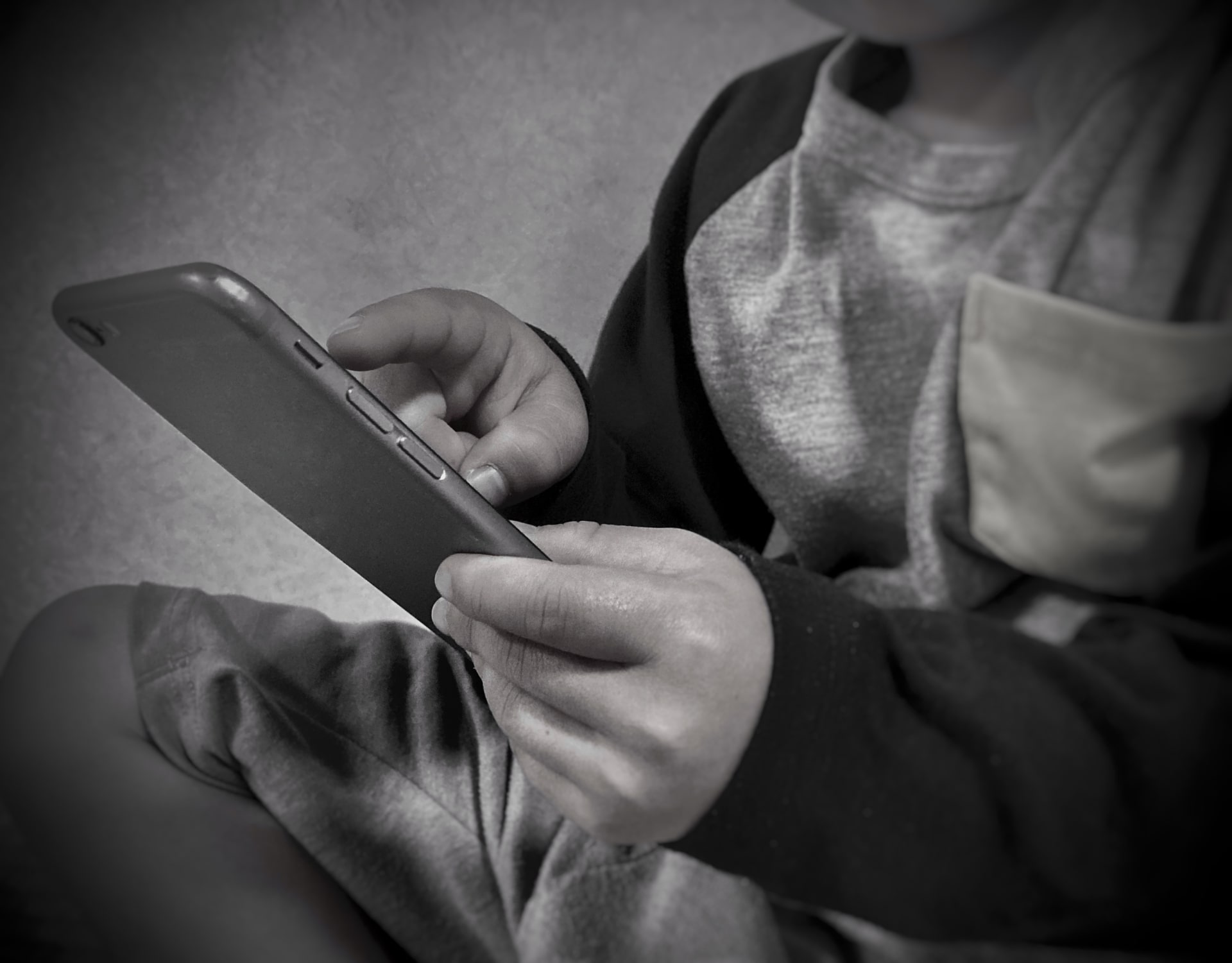
昨今よく聞かれるようになったスマホ依存。スマートフォンの利用の低年齢化により、スマホ依存は大人だけではなく、子どもにとっても深刻な問題に。スマホが子どもに与える影響を懸念して、世界の各国でSNSの利用規制や学校での使用規制が広まっています。
自分の子どもがスマホ依存にならないようにするにはどうしたらいいのか、親としては気になるところですね。今回はその予防策をご紹介していきます。また、「スマホ依存かも」と思ったときにどう対応したらいいのかも解説。まずは親がスマホ依存について理解することで、子どもに正しいスマホとの付き合い方を教えることができるでしょう。
スマホ依存とは
「スマホ依存」とはギャンブル依存症やアルコール依存症と同じく、スマホにとらわれて「やめたくてもやめられない」状態に陥っている、ということ。より具体的に言うと、スマホのアプリケーションの使用がやめられない状態です。
韓国の研究グループによるスクリーニングテストを参考に、スマホ依存症の症状例を見てみましょう。
【スマホ依存症の判断スケールの一部】(※)
・意思に反して長時間スマホを使ってしまう
・スマホでSNSを見たりゲームをしたりすることに夢中になって、勉強が手につかない
・授業中などスマホを見ていなくても、スマホが気になって仕方ない
・スマホを持っていないと怒りっぽくなってイライラする
・常にスマホのSNSをチェックしないと不安
・スマホの使い過ぎで手首や首が痛い
「わが子にも当てはまる」「この傾向が出ている」という場合は要注意です。まだ大丈夫、という家庭も、放っておくと依存症になる可能性はあります。まずは、スマホ依存になる原因や背景、依存による影響を知り、対策を考えていきましょう。
(※)出典: Kwon M et al. The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PLoS One 2013; 8(12): e83558.
スマホ依存症になる理由とは
スマホは、昔の子どもたちが遊んでいたツールとは大きく異なります。さまざまな遊びがスマホ一つで可能に。ゲームやアプリケーションは刺激が強く、思わずのめり込んでしまうように緻密に計算されています。
双方向である点も子どもをひきつけます。SNSはそばにいなくても友だちとやり取りができ、不特定の人との出会いも可能です。発信することで承認欲求が満たされることもあるでしょう。オンラインゲームで世界の人と簡単につながることもできます。
このような刺激的で楽しみが詰まったツールでも、大人であればある程度自制しながら使うこともできるでしょう。ですが、子どもの脳はまだ発達途中。やりたい、気になる、といった欲求をコントロールできず、次々と与えられる刺激や楽しみにはまり込んでしまうのです。
スマホ依存になるとどうなる?
スマホ依存は、子どもの心身に深刻な影響を与えます。本人だけではなく周囲、親をはじめ家族に影響が出てしまうことも。どのような症状が起こり得るのかを把握しておきましょう。
視力などに悪影響が出る
長時間にわたってスマホを見続けると目が疲労し、ドライアイや視力の低下につながります。文部科学省の令和4年度の調査によると、小中高生で裸眼の視力が1.0未満の割合は過去最悪という結果に。その原因は、タブレットやスマホなどデジタルデバイスの利用増加と言われています。
また、正しい姿勢でスマホを使わないと、猫背、ストレートネック、巻き肩などにつながることもあります。
記憶力が悪くなり、成績が下がる
スマホに夢中で宿題も自主勉強もできず、成績が下がる子どもも少なくありません。勉強に割く時間が少なくなってしまうほか、スマホからの大量の情報にさらされていると脳が疲労し、集中力や記憶力が低下するとされています。
睡眠不足などで体調が悪くなる
寝る間も惜しんでスマホを使っているため、慢性的に睡眠不足の傾向に。寝る直前まで画面を見ていると、内容の刺激や画面の明るさで脳が眠るモードになりにくいという影響も。また、スマホを触りたいがために食事もおろそかになってしまう子どももいます。睡眠と栄養が不足すると免疫力が落ち、体調を崩しやすくなってしまうのです。
コミュニケーションがうまくとれなくなる
スマホばかり使っていて、人とのリアルな交流が減ると、コミュニケーション能力は自然と低下します。特に幼い年齢からスマホに夢中になると、発語が遅れるなど言語発達の妨げになる可能性があるのです。
また、スマホでゲームなどに集中していると、脳の前頭前野の働きが弱くなるという研究結果も。前頭前野は感情を制御する働きを持っているため、スマホの長時間利用によって怒りっぽくなったり、自制が効かなくなったりという影響も考えられます。
劣等感を抱く
SNSでつながればつながるほど、たくさんの人の近況を目にすることになります。自分以上にたくさんの「いいね」を集めている、自分抜きで楽しそうに遊んでいるなど、投稿を見ることによって自身と比較し、嫉妬や劣等感を抱いてしまう子どもも。
親のお金を勝手に使ってしまう
スマホの有料アプリやオンラインゲームの課金で子どもが数十万~数百万も使ってしまった、という親の体験談もたびたび目にします。課金については管理していると思っていても、友だちに抜け道の方法を教えてもらう、親のクレジットカードを持ち出すなど知らないうちにどんどんお金を使い、高額の請求が来て初めて気が付くこともあるのです。

スマホ依存から子どもを守る! 予防と対策
子どもだけではなく家族も巻き込んだ大きな問題になるスマホ依存。そうならないように家庭でどう予防していくか、そして、子どものスマホ依存が疑われるときにどんな対応を取ればいいかを見ていきましょう。
スマホ依存にならないための予防策
これから子どもにスマホを持たせようと考えている人、すでに持たせ始めた人に向けて、家庭で取り入れたい予防策を紹介します。
「親から借りたもの」と理解させる
子どもにスマホを持たせることになっても、「あなたのスマホよ」と渡すのではなく「お父さん、お母さんから貸してあげるものよ」と伝えましょう。連絡をとったり安全を確認したりという必要性があるから、親が子どもに持たせているのだということ、自分のものではなく、親から借りているということを説明します。だから好き勝手に使えるわけではなく、親の意見も聞く必要がある、と理解させるのが第一ステップとなります。
子ども部屋ではスマホを使わせない
長時間のスマホ利用や不特定の人とのやり取りをしていても、子どもが自室で使っている場合は親にはわかりません。そのため、「スマホ利用はリビングのみ」と決めている家庭もあります。特に小学生以下の場合は、親の目が届くところでの利用に限ると安心です。充電する場所をリビングに限定するのもいいでしょう。
利用時間や場所のルールを子どもと一緒に作る
スマホを長時間使ってしまうのが依存の主な問題なので、利用時間を制限することは手っ取り早い対策です。iPhoneではスクリーンタイム、AndroidではDigital Wellbeing(デジタルウェルビーイング)という名前で、スマホの使用時間や利用範囲を制限できる機能が備わっています。
大切なのは、この機能で親が勝手に使用を制限するのではなく、子どもと相談して決めること。友人とのやり取りは何時くらいが中心なのか、どの程度時間を取れればいいのかなどを聞いて、子どもも納得したうえで利用時間のルールを決めれば、守られやすいでしょう。
食卓やお風呂にスマホを持ち込まない、ベッドの中では使わないなど、使用する場所も相談して決めましょう。
決めたルールは紙に書いて貼るなどして、常に目に見える状態にしておきます。
ストレスをかけすぎない
塾や習い事で毎日が忙しく、自分の時間が取れない子どもは、ストレスからスマホに没頭してしまうことも。子どもに無理をさせすぎていないか、勉強で追い立てていないか、親は今一度考えてみることが必要です。
スマホ以外の楽しみを一緒に見つける
「スマホばかり見ない!」と叱っても、それ以外の時間の使い方を知らなければ、結局スマホを手に取ってしまうことに。スポーツ、アート、音楽、読書など他に楽しめることがあれば、自然とスマホの使用時間は少なくなります。
「スマホを見ない」ではなく、「一緒にバドミントンをしよう」「美術館に行こう」など誘う声掛けをしてみてはどうでしょうか。子どもが打ち込めるものを見つけるきっかけと時間を作ってあげられるといいですね。
スマホ依存になってしまったら…5つの対応策を紹介
自分の子どもがスマホ依存かもしれない、と思うと不安になって、親はつい冷静さを失ってしまうことも。しかし、親の対応の仕方でよりこじれてしまうケースもあります。そうならないために、覚えておきたい5つの対応策を紹介します。
スマホを取り上げてしまうのはNG
無理やりスマホを取り上げるのはもっともよくありません。子どもは「親からひどい仕打ちをされた」と反発し、心理的な壁を作ってしまいます。部屋に閉じこもってしまったり、暴言、暴力がエスカレートしたり、隠れてスマホを手に入れようとしたり、問題は深刻化してしまうのです。
「スマホ依存」になっていることを自認させる
周囲から何を言われても、子ども自身が「自分はスマホ依存だ。なんとかしないといけない」と思わなければ、なかなか改善は難しいもの。まずはその認識ができるように、話し合いの機会を設けましょう。親は怒らず冷静に、子どもの思いを引き出すように問いかけます。
「一日何時間くらい使っているのか、この一週間を思い出してみようか」
「どうしてスマホをずっと触ってしまうんだろうね」
「スマホを使わないと不安になることはあるの?」
「スマホを使わなかったら、どんな過ごし方ができると思う?」
こうした問いかけの中で、子どもは自らのスマホ利用を振り返り、問題点が見えてくることもあるでしょう。
否定せず、子ども自身に答えを探させる
子どもがスマホに依存してしまう理由はいろいろあるでしょう。「友だちに仲間外れにされたくない」「スマホ以外におもしろいことがない」など。それを否定することなく、「そうなんだね」と受け止めてあげることが大切です。そのうえで、子ども自身は今後の生活をどうしたいのか、理想の状態にするにはスマホの利用をどうしたらいいのかを自分で考えさせます。親は子どもが考えをまとめやすいように適切な質問をし、アドバイスや考えを押し付けないように注意を。そうして、子どもが自分の中から答えを導き出すのを我慢強く待ちましょう。
少しでも改善したら、たっぷりとほめる
子どもと一緒にスマホ利用のルールを決めたら、それが守られているかどうかを親はチェックするようにします。もちろん、いきなり完ぺきに守れるわけではなく、ついルールを破ってしまうこともあるでしょう。そうであっても、できなかったことにフォーカスするのではなく、少しでもできたことを認め、ほめてあげることが大切です。
「目標をオーバーしたけれど、昨日よりも使用時間は少なかったね」「11時までに寝られたね。明日もがんばろうね」など、寄り添い励ます親の言葉が、子どものやる気を引き出します。
場合によっては専門家に相談を
スマホ依存が進んでしまうと、親だけで解決することが難しい場合もあります。そんなときは、依存症を診察している心療内科やメンタルクリニックなどを受診し、専門家に相談するのをおすすめします。近くに適当な医院が見つからない場合は、地域の子育て支援センターなどで相談してみるのもいいでしょう。
ただ、嫌がるのを無理に連れて行くのはNGです。病院に行けば専門家が助けてくれること、受診することで一緒に解決への道筋を考えてくれることなどを話して、不安を取り除いてあげましょう。
まとめ
「スマホ依存」は子どもとその周囲に大きな影響を与える
見てきたとおり、スマホ依存は「ちょっと長くスマホを使っているだけ」ではありません。子ども自身やその周囲に大きな影響を与える可能性がある、ということを、まずは親が理解しておきましょう。
親は寄り添い見守る気持ちが大切
子どもがスマホに依存していて、成績が落ちたりイライラしていたりすると親は不安になってしまいますね。でも、忘れてはならないのは理解し、見守る姿勢です。子どもと同じ目線で、どうしたら改善できるかをともに考えていきましょう。

株式会社ヘーグル 理事長
30年以上にわたって、幼児期からの理想的な能力開発と学習環境を追求、独自に開発した「親と子の共育大学のプログラム」など、親子でともに成長できる子育て、教育メソッドは絶大なる人気を誇る。

【執筆者】逸見 浩督(へんみ ひろただ)
株式会社ヘーグル 理事長
30年以上にわたって、幼児期からの理想的な能力開発と学習環境を追求、独自に開発した「親と子の共育大学のプログラム」など、親子でともに成長できる子育て、教育メソッドは絶大なる人気を誇る。








